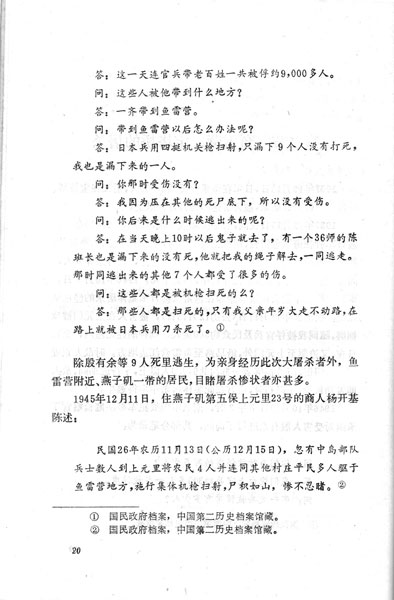東京裁判 魯甦供述書
〔通訳 証書一七〇二号其の儘読みます〕
〔通訳朗読〕
南京地方法院検事への魯甦に依る証言
敵軍入城後、将に退却せんとする国軍及難民男女老幼合計五万七千四百十八人を幕府山附近の四、五箇村に閉込め、飲食を断絶す。凍餓し死亡する者頗る多し。一九三七年十二月十六日の夜間に到り、生残せる者は鉄線を以て二人を一つに縛り四列に列ばしめ、下関・草鞋峡に追ひやる。
然る後、機銃を以て悉く之を掃射し、更に又、銃剣にて乱刺し、最後には石油をかけて之を焼けり。
焼却後の残屍は悉く揚子江中に投入せり。
此の大虐殺中に在つて教導総隊馮班長及び保安警察隊の郭某は縛を解きて逃亡し、佯つて地上に仆れ屍を以て自分の身を覆ひ難を免るを得たり。
但、馮班長は左肩に刺刀傷を、郭某は背中に火傷を負へど、上元門大茅洞に逃れ、私に由り便衣を求め、換衣して窃に江を渡り八卦州に至りて始めて危難より逃る。
当時、私は警察署に勤務しあるも、敵市街戦に際し敵砲弾により腿を負傷し、上元門大茅洞に隠れ居り、其惨況を咫尺の目前に見し者なり。故に此の惨劇を証明し得る者なり。
証人姓名 性別 年齢 原籍 職業 住 所
魯甦 男 卅三才 湖南省 政 南京義興路五号
※K-K註:極東国際軍事法廷速記録第58号1946年8月29日
『日中戦争史資料8 南京事件1』 p.141
南京地方院検察処敵人罪行調査報告
1 虐殺に関するもの
南京陥落に瀕せる当時、雨花台地区に在りし我方軍民二、三万は、退去に当り敵軍の掃射を蒙り、哀声地に満ち屍山を築き流血脛を没する惨状を呈し、又、八卦洲に於ては争ひて揚子江に渡り逃れんとする我軍民は悉く掃射を受け、屍体は江面を蔽ひ流水も赤くなりたる程なり。
陥落後、男女老幼五、六万人を幕府山附近数ケ村に監禁し、其飲食を絶ち、十六日、針金を以て二人宛縛し、四隊に別ちて草鞋峡に連行し 悉く機銃掃射を加へ、其上銃剣にて滅多刺に刺突し、更に石油を浴せて放火して之を焚き、残余の屍体は之を揚子江に投入せり。
又、陥落後、難民区内に在りし我軍民を駆って漢中門に連れ行き、網を以て縛したる後掃射を加へて殺害せり。
敵軍入城の日より起算し、集団屠殺二十余万人の外、凡そ我軍民にして未だ退去せざりし者は、敵人に遭へば必ず殺され、身を匿し居りて発見逮捕されし者は多くは刀剣の下に生命を失ひ、四肢と体とばらばらと成り血肉の区別も分らぬ如き状態と成り、此虐殺の惨状は実に有史以来未曾有の事なり。此外に、人民を強制徴発して軍役に使用し、自動車に搭載して何処にか運び去り、今日に至るまで八年、杳として消息を絶ちたるものあり。
之等は如何なる方式にて殺害せら<る>るや不明なり。
『日中戦争史資料8 南京事件1』 p.143
2 集団屠殺の証拠
南京陥落当時集団屠殺を行ひたる部隊は、
中島、畑中、山本、長谷川、箕浦、猪木、徳川、水野、大穂の九箇単位。
被屠殺者たる我同胞 二七九、五八六名
新河地域 二、八七三名(廟葬者盛世徴・昌開運証言)
兵工廠及南門外花神廟一帯 七、〇〇〇余命(埋葬者?芳縁・張鴻儒証言)
草鞋峡 五七、四一八名(被害者魯甦証言)
漢中門 二、〇〇〇余名(被害者伍長徳・陳永清証言)
霊谷寺 三、〇〇〇余命(漢奸高冠吾の無主孤魂碑及碑文により実証)
其他、崇善堂及紅卍字会の手により埋葬せる屍体合計 一五五、三〇〇余名
以上何れも別冊表に記載せるが如し。
埋葬地点及人数に関しては何れも極めて明瞭にして、且つ関係人の証言に依る。其情況を益々明白ならしむる為、特に関係機関をして各埋没地区の残存情況を撮影せしめたる写真二十余枚を添へて証拠となす。
『日中戦争史資料8 南京事件1』 p.143
鈕先銘『還俗記』
集団虐殺
抗戦中、日本軍の醜悪さを代表する三枚の記録写真があった。一枚目は、纏足をした一人の農村の婦人が強姦された後、殺されたもので、陰部に木の枝をつっこんであるもの、二枚目は一般の市民の服を着た一人の男性が目かくしをされ、ひざまずかされ、日本軍が軍刀をふるってくるのを待っているもの、三枚目は占領区の人民を生き埋めにしているところである。聞くところによるとこの三枚の写真はスライドフィルムにしてアメリカの各地で上映されたが、それを見た女性で悲鳴をあげなかった者はなかったという。
しかし、私の見聞きした日本軍の暴行はこの程度のものではない。戦争はもともと人を残酷にさせるものである。目を血走らせた兵士が精神に異状をきたして一種の虐待狂となり、強姦・掠奪と虐殺をおこなう。これは古今東西皆同じであり、歴史上にも前例のあることで珍しいことではない。しかし、この世でもっともむごたらしいことは、まだこれからだったのである。
二人の鬼子〔侵略〕兵が「進上」「進上」と言って盲目の和尚の一○八銀元を取りあげていったが、守印和尚の一晩の心痛はいかばかりのものであったろうか。これは彼の一生の蓄積なのだ。少なくとも彼は戦時にはわずかな財産があった。彼と二空が鶏鳴寺から永清寺に移ったのは二~三か月前だが、その頃は南京はまだ籠城していないだけでなく、上海・呉松一帯の戦場もまだ膠着状態のときであった。鶏鳴寺が通信施設として徴用されたため、彼らは永清寺に移り住んだわけだが、まだ平時といえる頃で、とくに警戒心はなかったのだ。南京籠城まで師や兄弟弟子たちにすら知らせていなかったのだから、籠城のときになってわざわざ隠すのも都合が悪いので、結局そのままにしてあり、このような破目になってしまったのだ。二空が私のために植木鉢の下に埋めておいてくれたお札のように運良くはいかなかったのだ。
あの夜は一晩、守印和尚と二空の嘆く声だけが聞こえ、守志先生と施先生もしずみがちで、年老いた農民は人を羨望のまなざしで見るようなおももちであった。私はと言うと、私も一晩中眠れなかった。私はもちろん敵軍の慈悲などに期待してはいなかったが、しかし、わずかこの二四時間内に虐殺・強奪が数えきれないほどおこなわれるのを見て、心が熱くなるような、それでいて逆に冷めていくような感じだった。また小グループのなかで人によって私へのあつかい方が同じでないことも、すべて私に恐怖心をもたらすのであった。
二日目は一日何の異状もなかった。敵軍は、何組かに分かれて市内を巡回していたが、それもまったく型通りにおこなわれていたし、その間隔もだんだん広くなりながら一群ずつ過ぎて行った。もっとも多いのは、ただ頭を突っ込んでまき小屋を見ることで、入って来てかきまわしたり査問したりすることはなかった。
しかし夜に近い、夕陽の沈む頃、突然一群の鬼子兵がやって来た。武器は何も持たず、ただオノとのこぎりを持って来て、我々のいた六畝ほどの寺の庭で、たくさんのザクロの枝を切っていった。長さは五~六尺、先にまたのついた枝を持っていった。
「あんな物を何に使うのだろう?」二空がまっさきに首をかしげた。
「たぶんまた新がいるんだろう。」施先生が想像して答えた。
「それならなぜ、我々のまき小屋にはまだたくさん新になっているのがあるのにそれをもって行かないのだろう。」守志先生が納得のゆかない様子で言った。私も、「私は何かテントのようなものの支えにするのではないかと思うけど」と、それなりに憶測してみた。年老いた農民はまだ口を開かず、守印和尚はただ黙々と我々の話を聞いているだけであった。
しかし、別にそのことがとくに我々を憂うつにさせるというほどのことでもなかった。 月は明るく、星影はまばら、かささぎが南の空に飛ぶ、これはたしか曹孟徳の詩だったと思う。南京が敵の手に陥ちたのは十二月十二日、だいたい農暦の十一月十五日前後にあたる、まさに月の明るい星影のまばらな夜だった。
夜も更けた。我々は大勢の人馬が入り乱れて歩む音を聞いた。ちょうど道路に沿って東へ下ってゆく。おそらくまた上元門から出て来た部隊であろう。ちょうど山に沿って十二洞に向かい、あの道を歩いて行った。月夜を利用しての駐屯の交代ということもあるので我々はさほどの注意も払わなかった。それに、まだ永清寺の区域の中までは入って来ておらず、ただ横を通っただけだった。
人声が過ぎ去ってからかなりの間静寂が続いた。我々はワラの敷き物の上でしだいに寝入った。
ちょうど夜中の零時から明け方までの間だった。突然重機関銃の音がした。距離はここから約一キロくらいのところだろうか。
「聞け」、私は二空を押した。
二空は起き上がったが、銃弾が上に飛んで来る気配も、寺の付近にとんで来る様子もない。「たぶん夜間演習でしょう。空砲ですよ。」と今度は二空はわかったように言ってグウグウとまた眠りこけてしまった。
この戦時に演習? 空砲?――私は疑いながらも、しかしそれが何であるかまでは想像できなかった。一晩が不安のうちに明けた。
決して講和せず
永清寺の下流一~二キロの沿岸に“大湾子”と呼ぶ場所がある。ここは非常に浅い砂洲である。流れが白鷺洲で二つに分かれているので、長江の本流は八掛洲の北側を流れており、中洲の南側を通る流れは、流れが緩慢で、そこに浅い砂洲を形成しているのである。
当然、あの機関銃の音がした日から一○日以上たってからであるが、我々はようやく、鬼子兵が大湾子で機関銃を用いて我らが同胞の俘虜兵二万以上を虐殺したことを知ったのだ。
読者諸氏は前述の、私と老年の農民が薪を上元門まで運ばせられたことを覚えておられるだろうか。あれは俘虜の炊事用のためのものだった。あのとき、私は自分の身の安否を心配するだけで、敵軍が俘虜をいかに処理するのかなど思いも及ばなかった。そして、そんなことは彼ら自身が考えればよいことだった。すでに俘虜となって武器を捨てたからには、せいぜい虐待と強制労働が待っているくらいで、生命の保障は当然のことだと思っていた。
誰がわずか二晩の後に大湾子に連行され、集団で始末されの犠牲者を出したが、その大部分は俘虜になってからのちにるなどと思っただろう!
あの晩、何も持たない鬼子兵が永清寺付近でザクロの枝を切っていたのは、一かためずつ死体を積み上げるための道具にするためだったのだ。
後日の不完全な統計によると、南京の役でわが軍は三○万虐殺されたものである。私がこの目で見た死体だけでもおよそ二万ほどあった。それが大湾子のあの死体の山である。
後になって私は後方に戻ったが、たびたび情報係の同志とそれまでの敵情判断をした。みんなの結論は、日本側は、すでに我々の首都を落としたのだから我々が当然講和に応じるものと思い、我々の人力と兵力を削減させるため、人道と国際慣例に反した集団虐殺をおこなった、ということである。
翌年一月中旬になってようやく日本の首相近衛文麿は国民政府と講和は結ばない、との声明を発表した。その間約一か月もの間、日本側は勝手に城下の盟を結べるものと思い込んでいたのだ。
「敗けても勝っても、ともかく彼らと講和は結ばない。」これは蒋百里将軍〔蒋方震〕の抗戦中の座右銘であった――百里先生は当時陸軍大学校の校長であった。空間をもって時間にかえる、それが私たちの司令官の最高方針であった。
ヒトラーがユダヤ人を集団虐殺したのは中日戦争の数年後のことであるが、あの虐殺は極めて科学的なもので、その死体処理は早くから周到に準備・計画されていたものであったため、事後に問題を残すことはなかった。しかし、鬼子の南京における大虐殺は、使ったのは重機関銃であったとはいえ、原始的とも言える殺人方法であったため、死体が山をなし、以後数か月にわたって処理する術もなく捨て置かれたものである。
鬼子兵が大湾子を虐殺場に選んだのは、あるいは長江の流れを利用して死体を流し去ってしまうためだったのかもしれない。しかし、冬の、水の枯れている――まさに蘇東坡先生の言う、山高く月は小さく、水落ち、石出づる季節に、しかも大湾子の流れはあのようにおそいのに、どうやってあんなにたくさんの死体を流し去ることができようか?
だから彼らは木の枝のまたを準備して何が何でも死体を長江に押し込もうとしたのかも知れない。日本人はこういうわざに長けている。読者諸君はまだいわゆる「白河流屍」事件を覚えておられるだろうか? あれは七・七開戦より二年前のことだった。華北の日本軍が北京・天津附近である軍事工事をおこなおうとしたが、日本から人を連れて来るわけにいかず、中国人を使ったが、軍事機密の洩れるのを恐れた。そこで何百人もの中国人を拉致して使役し、その後全部虐殺して口をふさいだ。「かわいそうな、無定河の河岸にただよう遺骨よ、まるで夢の中の人のようだ」。無定河は山西省の境に源を発しているが、桑乾泉からチャハル省をへて南に折れて河北省にいたると、“無定”という名をきらって永定河と名前が変わる。白河はその永定河の下流の合流である。
白河に流れた死体は三百体ほどで、しかも春、水かさの増す時期だったため、死体はすぐに海に流れ込んだので処理は比較的簡単であった。しかし、大湾子の方は二万を越すもので、木の枝で長江に押し込んだにもかかわらず全部流してしまえるわけもなく、結局あのように多くの屍体が浅瀬と砂洲のかたわらに滞積される結果となったのである。
南京大虐殺で殺されたのは不完全な統計によれば総数三十万ほどだという。しかしこれはまだ十分に正確とはいえない。しかし、永清寺の六畝の土地からだけでも四十数体の死体が見つかった。周囲一キロ平方の大湾子で二万以上が虐殺された。だから南京大虐殺で殺された人の総数が三〇万だというのは決して多過ぎるものではない!
一九四五年八月六日、あの天地をゆるがせた原子爆弾が広島に落とされたとき、その死傷者は国のおこなった正式の統計で、死者七万八千余り、負傷者および行方不明五万一千ほどであった。合計しても一三~一四万にすぎず、南京大虐殺の半分にも満たない。 日本軍の南京での残虐な行為は、広島・長崎の二つの原爆による被害者をたしてまだ余りあるものなのである。
原爆は、あのとき米国が戦争を迅速に終わらせるため、やむをえず使ったものである。初めの計画では東京・大阪・名古屋などの大都市に落とすはずだったのが、人道上の考慮で、広島と九州の小倉になり、小倉の一発は視界がたいへん悪かったので急遽長崎に投下された。この二つの原爆が日本人に与えた死傷は総数三〇万には満たない。
敗戦国は、原爆があのようにむごいものであったため、今でもなお米国の原子力潜水艦が寄港することを許さずにいる。それならば我々の南京大虐殺についてはどう言えばよいのだ?
徳を以て怨に報いるというが、日本に対して寛大すぎるため、今にいたるまで彼らの不人情をのさばらせているのだ。
死体の“臭票”
死体の処理は一―二か月たってからようやく実施された。正確な日にちは覚えていないが、大虐殺のあったあの夜は月夜だったから、暦で換算すると旧暦十一月十五日前後で、たしか新年まで約一か月半を残す頃だった。そういえば、元旦の朝、守志和尚の言いつけを守って釈迦像に礼拝するため、起きてすぐに廟の門を開けに行ったが、そのとき、よく廟の中をうろついている野良犬が、突然私の脇をかすめてとび込んで来た。私はびっくりしたのと腹が立ったのとで、犬の頭をなぐった。すると犬は口にくわえていた物を落した。下に落ちた物を見ると、それは乾ききった人間の足で、まるで仏手柑の枝のようだった。あのことから考えてみると、死体が完全に処理されたのは少なくとも旧暦の新年以後だったといえる。
ある日の昼頃、何人かの日本兵が一群の、腕に紅卍字会の記号をつけた中国人を連れて来た。彼らは廟の中まで来て、我々の中からも一人か二人派遣して共同で、集団虐殺された者の死体を処理するように要求した。この仕事は当然また私と二空が行かされることになった。
やって来た人の中に一人の日本人の和尚がいた。彼は、和服のような袈裟を着て頭に白い頭巾をまいて白い足袋と草鞋をはいており、手には、中国人の僧侶が使う磬のような、また小さな柄のついたドラのような楽器を持っていた。
永清寺から大湾子までは約一キロ余りの道のりである。その日本人和尚が先頭に立ち、楽器をたたき、念仏を唱えた。これはもちろん死者の魂の済度をするための読経であった。しかし、我々中国人和尚二人にはまったくかまわず、先に廟の門を入っても、菩薩を拝むわけでもなく、中国の釈迦牟尼すら彼にとっては拝む価値すらない、という様子だった。この従軍僧はすでに日本軍人の影響で一人の殺人鬼に仕立てられていた。ただ、残念なことに彼の手の中にあるのは仏教の楽器で、ライフル銃ではなかった。
我々が、大湾子に到る半分のあたりまで来た頃、死体の腐った臭いが漂ってきた。一緒に来た人や日本兵は皆、マスクを用意していたが、私と二空はハンカチすら持っていなかった。
季節はすでに厳寒に入っており、空気は乾燥していて雪も降らなかったので、寺の周りの死体はまるで大自然の冷蔵庫の中に放置してあったようで、腐乱していなかった。しかし、大湾子の死体は違った。一部は長江につかっており、砂洲の上のも、潮に浸蝕されて腐乱してしまったのだ。永清寺から長江の上流にあたる虐殺地点まで一キロ余り離れているので、冬の西北風が東南に向って吹いてもそこまで臭うことはなかったが、途中まで行くと臭いが鼻をついて耐えられなかった。
大湾子に近づくと、臭いだけではなかった。目で見て驚いたことに、山のように死体が一つの小さな区域の中に集められていたのだ。あちらこちらを向いて重っている死体にはまだ不完全ではあるが軍服が残っているので、肉体の状況ははっきりは見えない。しかし、顔の様子から見ると、ほとんど鼻がなかった。というのは腐爛は唇や鼻から始まるからである。門歯が外に露出してなかば骸骨のようなありさまであった。
私は虐殺当時の情況を想像することはできない! いくらたくさんの機関銃を使ってもこんなせまい場所で一度に二万人も殺せるわけはない。きっと何度かに分けておこなわれたのだろう。なぜ少しも反抗の叫び声が聞こえてこなかったのだろう。おそらく機関銃の音にかき消されて廟の中にいた私の耳に届かなかったのだろう。
あの日は、紅卍字会は第一回の視察をして、埋葬の方法を研究しただけであった。実際片付けを始めたのはそのあとで、一か月ほどかけて連続して少しずつおこなっていった。私はただ最初のその一回しか行かなかった。その後は用があるからと言って二空一人に行かせた。なぜかと言うと、私はニセ和尚で、中国人から見るとどうも簡単に見抜かれそうだったことと、あの悲惨な様子を二度と見るにしのびなかったからだ。
しかし、死体の衣服の中から思わぬ財産が見つかることがよくあったので、その後避難先から帰って来た多くの一般市民は、自分たちから希望して手伝ったりしていた。その後、南京で、「臭票」と呼ばれる色のあせた、いやな臭いのする貨幣が流通した。これらはすべて中国・中央・交通・農民各銀行から発行された本物の貨幣で贋札ではない。これはみな死体の中からひっぱり出されたものである。もちろんそのおかねは大湾子の二万の死体の中から見つかったものだけではない。南京の役では二、三十万の犠牲者がいたのだから、そこから出て来た臭票の数も、考えただけでも相当なものである。
〔鈕先銘『還俗記』より〕
〔井上久士訳〕
『南京事件資料集2 中国関係資料編』 pp.238-244
柳劍鳴(鈕先銘)の証言(崔萬秋『抗戦第二年代』 より)
説明
本書の著者である崔萬秋は、1903年山東省生れで、1924年に日本へ留学(広島高等師範学校、広島工芸大学)、中国へ戻って編集者・大学講師を務めたが、日中戦争期には国民党中央宣伝部へ入った。戦後はチャイナ・タイムスの副社長兼編集長、復旦大学で非常勤教授を務めた人物である。
本書は自伝小説であり、タイトルの『抗戦第二年代』とは、日中戦争の開始年である1937年を第一年代と数え、タイトルの『第二年代』とは1938年を意味するもので、1938年代の崔氏の生活、政治活動、交友等の記録である。この文章は、戦後には「抗戦外史」(仮題)として出版する意向だったが、1941年秋に『重慶時事新報』の文芸欄「青光」で連載小説が必要となり、この文章を掲載することになった。1942年冬に連載を単行本として出版したのが本書の原典となる(本書自序より)。
ここに掲載した柳劍鳴証言は、崔(文章中では葉惟明としている)が漢口の「役所」(中央宣伝部)に務めていた時に、旧友の湯肖民・錢際雲から晩餐に誘われた先で、突然、姿を現した柳劍鳴が語ったものである。柳は南京戦に参加した後に消息を絶った為、世間では戦死したものと思われていた。晩餐会の出席者が驚く中、柳が語った南京戦での顛末がここで紹介する証言である。
本書では「柳劍鳴」と書かれている人物は、実際には、鈕先銘であることは一部で知られている話だ。この「柳劍鳴」という名前は、詩人・作家である森三千代の小説「あけぼの街」「新宿に雨降る」に出てくる人物名である。本作は森の体験をもとに書かれたものと言われ、いわば私小説ということになる。森は新宿でアパート住まいをしている時に、陸軍士官学校に留学中の鈕先銘と出会い恋愛関係となるが、鈕の帰国後、連絡が途絶えるようになったという。森三千代に関しては下記記事に詳しい。
李イ〔火偏+韋〕「尋求「棄作」中的「記憶」――以森三千代的《曙街》為中心」
証言の内容は『還俗記』とは異なり幕府山事件に関する内容は少ないが、当時の中国軍将兵が南京戦でどの様に戦ったかを知ることが出来る内容となっている。本書では人物名に変更が見られるが、原本で変更されているのか、訳出時に変更を加えたのか分からない。鈕先銘の名前を、森三千代の作品で使われた「柳劍鳴」へ変更したことを考えると、訳出時の変更なのかもしれない。
なお、本文を引用するのに際し一部の漢字を旧字から新字へ直してある。
[参考]
「崔万秋」
(百度百科)
李イ〔火偏+韋〕「尋求「棄作」中的「記憶」――以森三千代的《曙街》為中心」 (壹讀)
(文責K-K)
本文
「ええ、ふるいむかしのことは、さて……といたしまして……
――十二日の午後四時のことである。陰鬱な天気だつた。前線の砲撃は午前中に較べて少し收つていたが、機関銃の音だけは激しくなつてきた。その三日前に、光華門の城壁のトンネルに突入した八人ばかりの敵と、一挺の重機関銃のため、払暁には我が某聯隊の小隊附樸存徳と、四人の兵士壮烈なる犠牲となつて敵の重機とともに自爆を遂げたのである。お陰で、光華門の局部的な戦況は、完全に危険状態から脱して安全となつた。
僕は戦況がやや落着いたことと、前日負傷した大隊附の黄由宇の病態が気に掛つたので、光華門から一時鼓楼の大隊本部に帰つた。そして今後の給与、弾薬の補充もするついでに、四五日間腹一ぱい食つたことのない胃袋にも補給してやろうと考えた。
六時頃だつた。富貴山にある總司令部から電話がかかつてきた。参謀長から緊急用務のため、至急に来い、ということである。僕は早速總司令部へ赴いた。参謀長は部屋にいた。その部屋には、各級幹部がぎつしり詰めかけていた。ひとしく誰の顔にも、緊張と憂鬱の色が漂つている。参謀長の説明では、右翼に於ける戦局が激烈で、中華門外の雨花台は敵手に落ち、光華門は大丈夫とはいえ、中山門外天宝城の第三方面左支隊は、既に敵の包囲のため混乱状態に陥つている。只今、衛戌長官の命令により、九時より退却を開始する。よつて各隊は各個に渡河を決行、浦口の鳥衣に集結して命令を待つべし。という意味のことが伝えられた。
次いで、各級幹部は夫々個別に命令及び指示を受領すると、相継いで退出した。最後に私の番がきた。参謀長は、「何人兵がいるか?」と尋ねたので、「三個聯隊」と答えると、「死傷者の具合は?」と問う。「異常なし、士気至つて旺盛」と答える。すると、「それは非常に結構だ」といつてから、「光華門は敵の攻撃の重点である。若し今夜にでも敵に突入されたならば、全般の退却計画は水泡に帰してしまわねばならぬ。謝承瑞の兵団は、この一週間の頑強なる抵抗により、三分の二以上の損失を出している。もはや、これ以上防禦線をもちこたえる力はあるまい。そこで貴官には明払暁迄抵抗して頂き度い」ということになつたのである。
軍人は服従を以て天職とする。この千鈞一髪の危機に際し、僕には勿論辞退すべき理由もない。ただこの重大且つ困難なる任務が達成できなくして、大局に累を及ぼしてはならぬと心配した。僕は唯一言、「ハイッ!」以外何もいうべき言葉はなかつた。
参謀室をでようとすると、彼はもう一度私を呼戻していつた。「もし夜半の一時以降になつて、情況が許せば、大隊本部を連れて先行渡河し、收容の準備に当るがよい」と附け加えた。僕は参謀長の好意にすつかり感激して、しつかり彼の手を握りしめた。そして急いで総司令部を飛び出したのである。
大急ぎで光華門の前線に帰ると、軍の企図及び我が部隊の退却援護任務を、三名の聯隊長に伝達し、更に一コ小隊を抜いて、必要な器材を先行させ、渡河準備に当らせることにした。
七時から十時までの間は、戦局も割合に閑散だつた。しかし十一時になると、急に砲声が激しくなりだした。城壁の上にいた工兵がバタバタと敵弾に倒れた。敵は既に光華門に突入して、五日間にわたる攻撃を続けているので、闇夜でも真赤に照らされた大隊本部附近に対する敵の砲兵射撃は、非常に精確であつた。我が方は既に野砲級以上の砲声は聞えなくなつてしまつている。重機の銃声ですらめつきり減つている。防禦線の部隊が減少したことは心細いが、逆に安全に退却してくれた証拠だと思えば却つて慰められた。
陰暦ならば十日前後であろうか。新月は西に沈んでしまい。微かな残光が、城壁上を見えつ隠れつして前進してくる敵兵の姿を透して映している。我が軍退却の企図を察知したのか、敵は払暁を待たずして攻撃を開始した模様である。夜半一時になると、中華門方面は、天をも灼き尽さんばかりの大火災を生じた。砲声もその附近が殊に激しい。敵は攻撃の重点を、光華門から中華門に変更したらしい。新街口以南では、次から次へと大炸裂音が聞えてくる。百米と距てた先は、全然不明だ。僕はニコ分隊の兵を派遣して、捜索に当らせたが、とうとうこの兵士らも遂に誰一人として帰つて来なかつた。
三時になつた。下関方面の火災は益々大きくなり、城内では幾所からも火光が見える。主力が撒退を始めてから既に六時間以上を経過している。おそらく大半は渡河を完了したに相違ない。払暁までは光華門から侵入してくることはあるまい。以後になれば、残留を命ぜられたこの三個聯隊は渡河の希望をなくする。そう考えた私は決心をした。先ず極く少数の兵力を残置して敵を阻止させる。自分は三個聯隊を集合させてユウ〔手偏+邑〕江門へいこう。
ところが、途中、盲滅法の乱射乱撃に、敵も味方も区別がつかず、泡のように湧いて出た乱兵が、目標もなく右往左往している。おかげで、我々がユウ〔手偏+邑〕江門に着いた頃には、友軍の乱射のために兵力は半数そこそこになつてしまつた。全くユウ〔手偏+邑〕江門に於ける惨状は、目もそむけたいばかりに酷いものであつた。
どうにかして下関に着いたものの、渡河材料が全然手に入らない。止むを得ず、筏を組んで三々五々各個渡河に移つた。ところが揚子江の水流はなかなか急である。とうとう僕の乗つていた筏が、河の真中まで来て、転覆してしまつた。水泳の技術は僕には自信がない。僕はすつかり溺死するより路はない、と諦めていた。だが僕は満足だつた。かゝる惨敗を喫したからには、死は当然の罰である。かくして、揚子江を浮き沈みつすること約一時間あまり、辛うじて葦の生い繁つた沙洲の上に漂着したときには、疲労の挙句、人事不省に陥つていた。どうして俺は河のど真中で死ねなかつたのか、天の恥辱だ、と恨しくさえ思われた。
江岸には、小さな廟がたつた一軒だけあつた。本堂は荒れ果て、仏像が地上に転つたまま、その辺一面は軍装品や、こまごました遺棄品が散乱していた。附近の公路上には、往来する人影が見える。遠くからも、近くからも、銃声が絶え間なく響いてくる。この廟には誰も住んでいないのじゃあないかと疑われた。
廟の右側は一間の茅屋になつていた。内部は真闇で、人影も見えない。首をつき込むようにして覗いていると、突然、ガタッ、という音がした。そして声がして、
「此処は出家どもの場所でございます。お入りになつては厄介なことに相成るでございます故……」
「ええ、承知いたしております。ただ誰方かお一人おいで願えませんか?」
すると、三十歳余りの坊さんが一人出て来た。僕は戦争に敗れたこと、この水に濡れた軍服の着換えが欲しい、等ということを申し出た。件の僧は、僕の姓名、原籍、軍隊番号、階級等を問い正した。僕はいちいちすばやく返答した。勿論全部嘘ばかりである。すると、その坊さんは一度茅屋の内側に帰つていつたが、再び出て来ていつた。
「お留め申し上げてもよろしいでしょう。ただ着物と仰言つても、僧侶のものがあるだけですが、どうせ着換えるからには、綺麗さつぱり変装したほうが、疑われなくつて好都合でしょう」
僕はことがこんなに順調に運ぶとは、思いもよらなかつた。そのときばかりは、すつかり感激の涙に咽んだ。
茅屋には五人の僧侶が住んでいた。四人までは五十歳以上の老人、その内二人は七十歳前後で一人が盲目、二人は小柄な田舎風体の老人だつた。もう一人が、私と口をきいた若僧である。後になつてわかつたことだが、盲目の僧老が若僧のお師匠さんだつた。彼は湖南の人で、庚子の年には、北京で大隊長をやつたとのこと※、彼が北京時代の中国青年たちが外国の侵略に対して抵抗したときの失敗を回憶してくれたのが、僕を収容してくれた動機であつた。もう一人の老僧は、彼の弟子で、やはりこの廟、永清寺の住職であつた。盲目の坊さんは、その弟子であつたとのこと。元来は台城の鶏鳴寺に住んでいたが、戦乱の為にこの田舎寺に移つてきた、ということであつた。
其処は八卦洲対岸の沙洲になつていた。下関からは八里下流に当る。上流には、ほどない距離に上元門があり、そこを南に五里程行くと、和平門の停車場に通する。
次の日、即ち十一月十四日の朝になつて、敵兵がやつて来た。公路上に於て、通行人と敗残者の兵隊が大勢虐殺された。我々のところは廟であつたため、物品をかつさらわれた以外、生命には別條なかつた。その日からは、殆んど連日のように敵兵が偵察にやつて来た。同時に、八卦洲にも行つて掠奪強姦の限りを恣にした。
※明治三十一年、北京に起つた義和団の事件を指す。
我々は、昼間は敵の搜索に応待し、夜分は灯のない稲の束の中に入つて一緒に休んだ。たまたま庚子以来中国が蒙つた列強の侵略問題に話題が及ぶと、盲目の老僧と僕とは、たとえ時代こそ異なれ感覚は同じであつた。兵敗れ、城陥ち、妻子が虐殺の目に遭つている時、己だけは身一つになつて、辛うじて俘虜の恥しめから免れたのである。それからは気も心もめいつて、遂に宛平の小廟に出家することになつた。というのが、彼の半世の経緯である。
彼はしきりに僕にも、出家してはどうか、そうすれば弟子にして上げる、と勧めてくれた。絶望のどん底に於ては、宗教こそ無上の慰めであろう。それで僕も、敵兵が搜索にくる度毎に、宗教的観念のお蔭によつて、自己の精神を鎮めることができたのである。決して僕は迷信を信仰するものではない。ただこうしていなければ、一秒だつて住みこんでいるわけにはいかなかつたのである。
永清寺に住みついてから、約一カ月が経つた。恩師守印と師兄二宮とは、鶏鳴寺の廟産を棄てるには忍びないとみえて、遂に一策を講じ、城内に入つて探りをいれてみることになつた。その結果は、比較的良好だつた。そこで私も遂に二月の末、幾多の困難を突破して、鶏鳴寺に移住したのである。
毎日、景陽楼の上に登つて、はるか彼方台城のほうを眺望すると、まことに杜工部の詠める「国破れて山河あり、城春にして草木深し」の光景そのものであつた。
光華門に於ても、下関に於ても、はたまた揚子江に於ても、死に損つた僕は、肉体のみは依然と備わつていても精神はすつかり藻抜けの殻だつた。朝な夕な、金剛経を奉誦するのが日課だつた。「人生如夢幻泡影、如露亦如雹、一切有為法、応作如是観」僕は残りの人生は出家して、とまで思い立つた。しかし、天意はいつまでも愉安を許さなかつた。即ち第一に、恩師守印は三月病気のために円寂してしまい、僕は信仰の保障を失つたこと。第二には、敵が常時うるさく、我が軍人を隠匿してはいないかと、捜索の眼を鋭くしてきたためであつた。難民区では、その件で、既に無数の惨事が惹起していた。師淑の守志と、師兄の二宮が相談した結果、双方の安全のためにというわけで、僕を虎口に送り出すことに決定したのである。
かくして僕は、種々の困難を経て、やつと敵の特務機関の証明書を獲得することができた。しかし、万が一を慮つて、師叔は六十九歳の高齢にかかわらず、自ら上海まで送つて来てくれた。汽車に対しては、敵のほうでも我が遊撃隊の活動を封じようとして、憲兵を以て、列車の出入口に対し厳重なる監視をさせていた。我々は十一時間というもの、水一滴を口にするでなく、便所へも碌々行けず、我慢辛苦の末、やつと上海に着いたのである。
北停車場は、依然として、くずれ、家傾ける慘澹たる光景であつた。途中我々は、十一回もの敵の守備隊の検査を受け、やつと外白波橋に到着、スカート姿のスコットランド兵の防備線をくぐつて、辛うじて、『孤島の天堂』に入つたのである――」
崔萬秋『抗戦第二年代』 pp.101-110
唐光譜「私が経験した日本軍の南京大虐殺」
私は唐光譜といい、原籍は江蘇省阜寧で、南京の北郊外にある六合県竹鎮に住んですでに四十数年になる。一九三七年、私はまだ一九歳で、日本軍の南京での大虐殺の惨劇を身近に経験し、今にいたるまでなおありありと眼に浮かぶ。
当時私は国民党の教導総隊第三大隊本部の勤務兵であった。大隊の上海戦場への出動にしたがって、江湾に駐留、守備にあたった。十一月上旬南京に撤退を開始した。私たちが南京に戻ってから一月もしないうちに、日本軍はまた南京に進攻してきた。十二月十二日、日本軍が中華門に攻め入ると、南京の各部隊は包囲突破をするものは突破し、撤退するものは撤退し、市内の混乱ははなはだしかった。私と六人の兄弟は部隊との連絡を失い、そこで人々の流れにしたがって下関方面に逃げた。その中に唐鶴程という塩城の人がいた。私とはいたって親しく一緒に避難し、たとえ死んでも離れないことをともに約束した。私たちがユウ江門の外に来たとき、城門の入り口は人の流れでぎっしりと詰まっていた。おしあいへしあいしたときに足をひっかけられて倒れる人もあり、人々がその身体の上を踏みつけていくので、もはや立ち上がれなく なっていた。この情況を見て、私たち六人はゲートルで互いの腕を一緒に縛り、もし誰かが倒れたら両脇の人が引っ張り上げることを約束した。このようにして私たち六人は一緒におしあいへしあいしながらユウ江門を出た。
下関の河辺には人がたくさんいて大通りも路地も立錐の余地もないほどで、眼前に大河を望んで人々はどこへ逃げればよいかわからなかった。私たちも人の流れにしたがってむみやたらと走った。このとき、大きな馬に乗った大役人が群衆の中をつき進み、マイクを使って、「兄弟たちよ、命が助かりたかったら、私についてこい!」と大声で叫んだ。ばらばらの兵士たちは役人の指揮を見ると、少し鎮まった。その役人は軽・重機関銃隊に道を開いて先導させ、歩兵が後につづき、上新河の方向へ逃走していった。大量の敗残兵が上新河橋に着いたが、橋は狭いのに人が多いので混雑で多くの人は通り抜けられなかった。私と唐鶴程は押されて橋を渡ることができず、他の四人も雑踏で私たちとばらばらになってどこに行ったかわからなくなった。私たちは仕方なく、橋を渡れなかった兵士について、長江に沿って龍潭・鎮江の方に向かって走った。
私たちは背の高い葦を利用して身を隠し、河辺の葦の湿地の中をよろよろと前に向かって逃走した。私たちが橋の前まで来たとき、橋から遠くない城壁の上に日本人がすでに数挺の機関銃を設置し橋を封鎖していた。橋を渡ろうとした多くの人はみな橋のこちら側と向こう側で撃ち殺され、血があたり一面に流れた。私たちは敵の掃射が止んだわずかな間隙に乗じて勢いよく橋を渡り、燕子磯に向かって走った。燕子機の町に着くと、すでに人影は一つも見えなかった。私たちは厚い肉切り板を探しだし、二人であらん限りの力を出してやっと河辺まで運び、水中に引き入れそれに掴まって河の北まで渡ろうとした。私たちは一生懸命やって精根つきはてたが、依然南岸に漂っていた。仕方なくまた燕子機に戻った。
空は暗くなり、殺人の銃声はだんだんと近づいた。私たち二人は懸命に山にかけ登り、穴の中にうずくまり一つも音をたてなかった。だが空がまだ明るくならぬうちに日本兵は山を捜索していて私たちを見つけた。町の中の空き地に私たちを護送し、背と背をあわせ腕と腕を縛りあげた。そこにはすでに私たちのように縛られている人がたくさん立っており、しかもさらに多くの人がつぎつぎと日本兵によって連れてこられ、縛りあげられた。その後、私たち二人はこの一群にしたがって、幕府山の国民党教導総隊の野営訓練臨時兵舎に連れていかれた。この臨時兵舎は全部で七、八列あり、すべて竹と泥でできたテントだった。中は捕らえられた人でぎっしり詰まっていた。私たちは中に閉じ込められ、ご飯さえ食べさせてもらえず、三日目になってようやく水を飲ませてくれた。敵は少しでも思うままにならないと発砲して人を殺した。五日目になった。私たちはお腹の皮が背中につくほどお腹が空いてみなただ息をするだけであった。明らかに、敵は私たちを生きたまま餓死させようとしており、多くの大胆な人は、餓死するよりも命を賭ける方がましだと考え、火が放たれるのを合図に各小屋から一斉に飛び出ようとひそかに取り決めた。その日の夜、誰かが竹の小屋を燃やした。火が出ると各小屋の人は皆一斉に外へ飛び出た。みんなが兵舎の竹の囲いを押し倒したとき、囲いの外に一本の広くて深い溝があるのを発見した。人々は慌てて溝に飛び降りて水の中を泳いだり歩いたりして逃走した。しかし、溝の向こうはなんと絶壁でありみな狼狽した。このとき敵の機関銃が群衆に向かって掃射してきた。溝の水は血で真っ赤に染まった。逃走した人はまた小屋の中に戻された。小屋は少なからず焼け崩れ、人と人は寄り添い近寄っておしあいするしかなく、人間がぎっしりと缶詰のように詰まり、息をするのもたいへんだった。
六日目の朝、まだ明けないうちに敵は私たちを庭に出し、すべての人の肘同士を布で縛ってつなぎあげた。全部を縛りおわると、すでに午後二時過ぎであった。その後敵は銃剣でこの群衆を整列させ老虎山に向かって歩かせた。そのとき人々は腹が空いて気力もなくなっていた。敵は隊列の両側で、歩くのが遅い人を見るとその人を銃剣で刺した。十数里歩くともう暗くなった。敵は道を変えて私たちを上燕門の河の湿地から遠くない空き地に連れていった。六日六晩食物を与えられず、たくさんの道を歩いたので、一度脚を止めるともう動けなくなって地面に座り込んで立ち上がれなかった。一時間の間、その場には数えきれないほどの人が座っていた。
このようであっても生存本能から、敵が集団虐殺をしようとしていることに感づいた。私たちは互いに歯で仲間の結び目を咬み切って逃走しようとした。人々がまだ全部咬み切らないうちに、四方で探照灯が点き、真っ黒な夜が急に明るくなり人々の眼をくらませた。つづいて河の二艘の汽船の数挺の機関銃と三方の高地の機関銃が一斉に狂ったように掃射してきた。大虐殺が始まったのだ。
銃声が響くと、私と唐鶴程は急いで地面に伏した。ただ多くの人が「打倒日本帝国主義!」「中華民国万歳!」というスローガンを大声で叫ぶのが聞こえただけだった。銃声・叫び声につづいて、多くの人が銃弾にあたって倒れ私たちに上からおおいかぶさってきて、私たちは下敷きになった。彼らの鮮血が私の衣装に染み込んできた。私は息を止め身じろぎさえしなかった。二十数分が経ち銃声が止むと、私は戦々兢々として唐鶴程を手探りして彼を引っ張り、低い声で「どうした?怪我はないか?」ときいた。彼は「大丈夫だ。君は?」と言った。話し声が終わらぬうちに機関銃の音がまた響き起こった。私は驚いて死人の山の中に隠れ身じろぎしなかった。二日目になって掃射は止まった。私は唐鶴程がちっとも動かないことに気づいて緊張した。私は力を入れて彼をゆさぶったが彼はそれでも動かなかった。彼の頭部に触れたとき彼の頭に弾があたっていることを発見した。鮮血が絶え間なく外に溢れ出てきた。私は驚き大急ぎで死人の山の中に引っ込めた……。
しばらくして銃声は聞こえなくなった。私は急いでここから離れなければ生き延びられないと思った。私はゆっくり、そっと死体の中から首をのばしてのぞき見た。前には死体がころがり私をさえぎっていた。私は前方に這っていけば敵に見つかるだろうと思い、脚を後方の死体に引っ掛けてゆっくりと少しずつ後に下がり、死体の山のところまで後退した。私は再び動こうとはしなかった。
探照灯はとっくに消え、暗く静かな夜が大虐殺によるこの世でもっとも悲惨な現場を蔽った。河の水がザアザアと流れまるで悲痛な泣き声のようであった。どれほど経ったかは知らないが、私は敵が物を片付ける音、つづいて彼らが歩く音に気がついた。汽船もドンドンと走り去った。私はやっと大胆になってゆっくりと歩いたり這ったりしながら、下流に向かって十数里歩いた。私は一つの洞窟のあたりにたどりついた。ふと見ると、入り口にも敵によって殺害された同胞がごろごろところがっていた。私は多くを考えずに風を避けられる洞窟の中に這っていった。
ぼんやりと空が明るくなるのを待ち、またぼんやりと正午まで待った。私は一艘の小舟が洞窟の方に揺られてくるのを見つけて飛び上がるほどびっくりした。岸についた船には老いたのも若いのもいたが、みな中国人であることがわかった。もともと彼らは南岸の人で、日本人から逃れてやっと対岸の八封洲に行ったのだが、敵のパトロール船がいないのに乗じて牛にやる草を載せて河を渡ってきたのであった。私はすぐに洞窟から飛び出してへさきに向かって走り、彼らに命を助けてくれるよう頼んだ。老人は私が満身血だらけなのを見てすこし狼狽したが、私を船室に隠して上から藁をかぶせ、私を八掛洲に連れていってくれた。
その後、幾度か危険を経て私はようやく六合県竹鎮に着き定住した。
〔『南京保衛戦』より〕
〔帆刈浩之訳〕
『南京事件資料集2 中国関係資料編』 pp.250-253
唐広普 教導総隊二団三営(インタビュアー 本多勝一)
唐広普さん(六八歳)は一九一七(大正6)年の旧暦一一月二〇日生まれ、江蘇省阜寧県出身である。 数え年一六歳で国民党(蒋介石)軍に入営したが、兵士としてではなく、いわば用務員として軍の雑務をしていた。日本軍の南京攻撃当時は陸軍軍官学校教導総隊二団三営(注1)の勤務員だった。「城防司令部」は新街口のにぎやかな商店街にある交通銀行におかれ、司令官は桂永清だった。(南京市駐屯軍全体の指揮官としては李宗仁と白崇禧がいて、この二人は唐生智より有名だったと唐さんはいう。)
唐さんはここで茶碗を洗ったり片付け仕事をしたりの雑務をしていたが、日本軍城内侵入の二~三日前に口令(伝令)として城外へ出たことがあり、そのとき初めて日本軍の戦車を見た。
一九三七年一二月一二日の夜八時か九時ごろ、城防司令部の軍官(将校)ら二〇~三〇人は、下級兵卒や勤務員たちに、「残って最後まで抵抗せよ」と命じ、自分らは馬で逃げ出した。だれも監督や命令をする者がいなくなったので、その後はばらばらになって勝手に出ていった。唐さんが同僚とともに六人で交通銀行を出たのは深夜の一時か二時ころだった。群衆にまじって大混乱のうちに中山路を北へ歩き、ユウ江門から出ようとした。
だが、門には国民党軍の戦車が一台破壊されて頓挫し、周辺は死体が層をなしていて、それをふみこえていく大群衆の人波がぎっしりと隙間なくつづいていた。いったん倒れたら人波にふみつぶされて助からない状態だった。死体の層は門のところが最も高くなる山になっていて、その高さはたぶん一メートか二メートル近くもあった。戦車の上にも死体があった。唐さんたち六人は、なんとかして倒れないように無事に出ようと、門のそばの空地へ行ってゲートル (巻脚絆)で互いの腕をしばった。こうすればだれかが倒れかけても両側から支えることができる。
このようにしてやっとユウ江門を通過した六人は、一〇〇メートルほど門を出たところでゲートルをほどき、ばらばらに逃げた。唐さんは同年輩の康鶴程と二人で逃げた。このとき群衆の一人から聞いた話だと、門の下に頓挫していた国民党軍の戦車は、群衆をふみつぶして逃げようとしたため、「抵抗もせずに真先に逃げるとは許せない」と、国民党軍の兵卒が手榴弾を投げこんだ結果らしい。大群衆は国民党軍の兵卒も市民もごたまぜだったが、どちらかといえば市民の数の方が少ない印象で、とくに女性はあまり見なかった。また兵卒たちの大部分はまだ軍服を着ていた。
ユウ江門から北の方へと逃げる途中、熱河路の入口あたりの壊れた自動車の中に毛端咾子(厚い毛織りの布)があった。寒いので、唐さんはこれを軍服の上から羽織って着た。濃い青色の高級品で、おそらく金持ちのものだった。康鶴程は軍服のまま上に何もつけなかった。
長江の岸辺に出た二人は、舟かそれにかわるものを捜しながら岸ぞいに下流へ(北へ)ゆくうちに、燕子磯あたりで夜があけた。舟の類は一切ないので、浮きになるような板か材木をさがして泳ごうとしたが、民家の扉など目ぼしいものは片はしから利用しつくされていた。ある一軒で料理用の卓をみつけたので、二人で岸辺にもっていって泳いでみたが、浮力不足で沈んでしまう。またもどって小さな木箱を二つみつけ、さかさにした卓の両側に結びつけた。こうして木箱の間の卓に乗ったかたちで、軍用の小型シャベルを櫂がわりにして漕ぎだした。ところが、こんなかたちでは舟のように進まない上に、沖の方からの逆風だったので、一○華里(五キロ)くらいまわった末に岸にもどってしまった。
こんなことをしているうちにその日は暮れた。疲れはてて路地ぎわに腰をおろすと、そのまま二人は眠りこんだ。
銃声に目がさめると、すでに薄明であった。銃声と反対の方向へ逃げてゆくと、そちらからも銃声がした。で、もう一方の側へ走ったが、これも銃声だった。どうやら包囲されているらしい。右往左往する群衆で大騒ぎになり、そんな中に軽機関銃の音もきこえた。
ついに日本兵の姿が現れた。カーキ色の軍服で、みんな馬に乗っている。騎兵隊なのだろう。軽機関銃を持った兵隊は丈の高い赤毛の馬に乗っていた。軍刀をふりたてる者が多かった。追いたてられる過程で射殺・斬殺される者も続出した。
燕子磯の街の西に野菜畑があり、群衆はそこに追いたてられた。ざっとみて三○○○人か四○○○人くらいが集められると、騎兵隊のほかに歩兵たちもたくさん現れ、全員の身体検査をはじめた。武器の類を持っている者などだれもいなかったが、多少とも貴重な目ぼしいものはみんな取られた。唐さんの着ていた毛咾子も奪われた。
身体検査が終ると、正午ごろになって四列縦隊に並ばされ、周辺を日本兵に警戒されながら歩きだした。 連行された先は一○華里以上離れたところにある草営房(草ぶきの大きな棟)の廠舎で、以前は国民党軍が訓練用の仮兵舎にしていたところだった。つめこめば一棟に二~三団 (注2)、 すなわち二○○○人以上はいると思われる草営房がたくさん並ぶ。床も寝台の類も一切ない地面だけの室内に、唐さんらは満員電車なみにつめこまれた。
この廠舎に以後一週間いることになるが、あまりにぎっしり詰めこまれているので、横になって眠ることができない。地面に敷くものもない。仕方なく立ったまま、まわりにもたれあって眠った。外に出ることができないので、大小便を入口近くの者は壁ぎわにしたが、奥の方だとたれ流しにしている者もあり、廠舎は惨憺たる状況となった。ただ飲まず食わずのため、大小便もあまり出なくなった。これでは餓死するので、せめて水をくれるように日本兵に懇願すると、四日目にようやく飲むことができた。しかし、年配者の中には死ぬ例もあり、死ぬと外の溝などに捨てられた。捕虜の一部が出されてどこかへ連行されたり、新しく連行されてきたりすることもあったが、他の棟とは連絡が一切とれないので、どこで何が起きているのか様子は全然わからなかった。
ここへ連行されてきた日を含めてたぶん七日目、すなわち一二月二〇日前後の朝、日本兵が「ここは食糧がないので、城内の食事できるところへ移動する」と告げた。移動の前に、全員をうしろ手にしばる作業がつづけられた。新しい白布を裂いてひもにし、大量の捕虜群をしばり終ったのは午後一時ごろであった。
兵隊らにはさまれて四列縦隊で歩きだした一行のなかで、唐さんはほぼ中央部にいると思われた。康鶴程もずっと一緒だ。行先が南京城内とは違うようなので「変だ」と思ううちに、上元門と草鞋峡のあいだにある老虎山 (注3)のふもとを通り、長江の方へ行った。一週間も食べていない捕虜群では歩くのにもよろよろして時間がかかったが、途中で逃亡する例は唐さんの知るかぎりでは一人もなかった。しかし衰弱のあまり歩けなくなる者があると、兵隊たちはしばっているひもを切って道ばたにひきずりだし、銃剣で刺し殺した。
途中で休憩があって行列がとまったとき、ある兵隊が唐さんのひもを切って列の外へつれだした。殺されるのかと思ったら、地面に三つんばいにさせられた。その背中に兵隊が腰かけると、理髪兵らしい男がその頭を刈りはじめた。終ると唐さんはまたしばられ、列にもどされた。
長江(揚子江)の川岸に着くと、行列は到着順にすわらされた。ところどころにアシのはえた湿地であった。もう夕暮れになっていた。曇っているので一層暗かった。ここが目的地であることを知って、唐さんもまわりの捕虜たちも集団虐殺は決定的だと思った。長江の岸辺には二隻の軍艦がいて、甲板に機関銃なども見える。暗くなるにつれて軍艦から探照灯が現場をてらしだした。
行列の全体が到着しおわっても、中国語による何らかの説明はきかなかった。唐さんのいる周辺でひそかに紐をほどく助けあいが始まった。はじめの人が歯で前の人のうしろ手をほどくと、ほどかれた人は手で別の人をほどく。唐さんのひもは手でほどかれた。このあたりは集団のほぼ中央だったので、日本兵の気づきにくい場所だった。
どういうつもりか、兵隊たちが枯草をまわりの立木などにひっかけはじめた。到着して一時間くらいたつと思われるころ、この枯草に一斉に点火された。ガソリンか石油でもかけられていたのかどうか分らないが、よく燃えあがって明るくなった。一斉射撃が開始されたのはそのときである。どの方向から何丁の機関銃などで撃ってきたのか知るよしもなく、唐さんも鶴程もすわっている姿勢から反射的に地面にはいつくばった。二人は肩をくんでいた。
一斉射撃が始まった直後は、銃声のほかはほとんど叫び声などきこえなかった。もがき苦しむ者が唐さんの背に倒れてくる。何人もが折重なった。
一○分か一五分か、唐さんにはたいへん長い時間と思われる一斉射撃がいったん止んだ。とたんに、それまで轟音でかき消されていた群集の声、地をゆるがすような大喚声がわきおこった。それは呻き声とも泣き声ともつかぬものだった。どうなったのか見まわすことはできなかったが、まだ生きていることは確かだ。肩をくんで這いつくばっていた康鶴程の耳もとに、小声で「大丈夫か?」とささやくと、「うん。痛みはない。大丈夫」という答えがあった。
たぶん四~五分ほどのち、一斉射撃が再開された。ほとんど同時に、唐さんは右肩に打撃を感じた。このとき弾丸が命中して貫通したのだが、すぐには痛みを覚えなかった。肩にできた二つの穴からあとで考えてみると、これは川岸の軍艦の上から発射された角度による弾丸が命中したものらしい。
二度目の掃射が終ったとき、康鶴程にまた小声でささやきかけたが、こんどは返事がなかった。左手でそっと彼の身体をなでると、頭が血にまみれている。もう死んでいた。康鶴程の死を知ったとき、はじめて自分の肩の痛みを覚えた。この段階になってもまだ呻き声、叫び声は各所から聞こえていた。すると銃剣をかざした兵隊たちが大勢で射殺してまわった。唐さんの周辺にも兵隊はやってきた。左の脇腹をやられた。さいわい他の死体の下にいたせいか浅い傷だったので、刺された瞬間は気づかないほどだった。肩の傷の痛みが激しいせいもある。あとで川にはいったとき水がしみて気づいた。
呻き声などがきこえなくなるころ、兵隊たちは群衆の死体からまわりに引き揚げ、軍艦からの探照灯が消えた。暗くなった。これで軍艦は去ったらしい。おそらく二〇分ほどのち、まだざわついている周辺からガソリンのような匂いがした。しかしそれが死体への放火のためだと気づいたのは、点火されて各所に焔が燃えあがった瞬間だった。猛烈な煙も発生して、呼吸が困難になるほどだ。このままでは焼き殺されてしまうので、唐さんは這ったままの姿勢で少しずつ移動した。頭の方(前方)は死体の層が高くて進めないので、足の方へあとびっさりにいざった。それは川岸の方向だった。兵隊たちはまだ去っていないので、火に耐えきれずに逃げ出す者は刺殺される。見つからぬようにと死体の間や上を這って、四○~五○メートル離れた汀までたどりついた。死体は川岸までぎっしり地をおおっていた。煙と火からようやく逃れた唐さんは、ここで足を死体の上にのせ、頭を水すれすれ、たぶん水まで三センチあるかないかの格好で、したがって上体がやや逆立ちぎみになったまま動かないでいた。
曇っている空は暗く、ときに小雪もちらつく夜だった。寒いので兵隊たちも火にあたっているらしい。やがて呼笛の音がした。集合の号令である。時間はよくわからないが、午前零時ころだったかもしれない。川とは反対の方にざわめきながら集まっていった。
岸辺には枯れたアシが生えていた。唐さんはひそかに水にはいり、ひざから腰ほどの深さの水中を、下流の方(東)へと岸ぞいに歩いた。何百メートルか水中を歩いたが、空腹と傷の痛みに耐えがたく、アシの生える岸辺にあがった。そのままこんどは陸上を岸ぞいに四~五華里ほど歩き、あるレンガ焼き窯(注4)をみつけて、その中にかくれた。窯のなかで居眠りするうちに、心身とも疲れはてていた唐さんは、そのまま深い眠りにおちこんでいった。目ざめたときは朝の一○時ごろであった。なにか川を渡るものがないかと岸辺に出てみたとき、沖の方から小舟が近づいてきた。日本兵かその関係者かもしれないので、あわてて窯にもどってかくれた。そっとのぞいていると、小舟は日の丸を立てていて、接岸すると老人と若者が上陸してきた。もし窯に来て見つかっては危ないので、唐さんはこの周辺にも散らばっていた死体の間に寝て、死体のふりをしていた。 二人はそばを通りかかり、この地方の中国語を話していた。これなら大丈夫とみて、唐さんは救いを求めた。老人に何度もおじぎをして助けを乞い、虐殺の様子と肩の負傷を説明した。
この二人は長江対岸の南の方にある八卦州の農民であった。牛を飼うために稲ワラの束をここへ運びに来たのである。唐さんの話に老人は同情し、舟にのせてくれることになった。負傷はもう大したものではなくなっていたので、舟までのワラ運びを唐さんも手伝った。近くに積んであったワラの束を両手に下げて、四回くらい往き来した。舟底に横になった唐さんを、二人はワラで覆ってかくしてくれた。
こうして虐殺現場から逃れた唐広普さんは、江蘇省六合県の竹鎮という所へ行って、乞食になった。あのような皆殺し現場から脱走できた者は、おそらく自分以外にはいないだろうと思っていた。半年ほど過ぎた一九三八年夏のある日、竹鎮の知合いの店主が唐さんを呼んで「このお客さんの広東語を通訳してくれ」といった。店に来ていた若い男客がここの言葉を話せず、店主は唐さんが広東語を解することを知っていたからである。紹介されたその客は、竹鎮の郊外から買い物に来たのだった。
このときの通訳がきっかけで、その「楚」姓の男客と唐さんは親しくなった。あるとき二人はたがいに身の上を語り、楚の過去を知るうちに、彼もまたかの長江の虐殺現場からの脱走者であることがわかった。
しかし楚の場合は、ガソリンの放火で背中に大やけどを負いながらの脱走である。その大やけどの跡が残る背中を見せてくれた。
一年ほどのちに、楚は新四軍(八路軍とともに人民解放軍の前身)に入隊する決意をかため、竹鎮を去った。唐さんは餞別に鉛筆と手帳を贈った。楚の消息はそれ以来わからない。彼の半年後に唐さんも新四軍に加わった。
<追記>
唐さんの話の中で、日付けや時間については、大騒乱のなかでのことでもあり、多少のずれがあるかもしれない、と当人が語っている。
注
(注1)教導総隊 陸軍士官学校の生徒らが戦闘訓練などをするとき、指導官見習いとしての生徒らに「指揮される側」として存在する訓練用部隊。
(注2) 藤原彰・一橋大教授によれば、国民党軍の一団は師団下の連隊にあたり、一団は一○○○人前後。
(注3) 老虎山長江ぞいのこの丘陵は、長江側から見ても「老虎」らしさはないが、南京城北東郊外の玄武湖公園あたりから見ると、いかにも虎の頭部のようなかたちをしている。
(注4) レンガ焼き窯 レンガをドーム型に積みあげた、高さ三~四メートルの窯。
<第二刷追記>
四三ページの「追記」で「この間の事情はまだよくわからない」と書いた虐殺者数のくいちがい (三二八人か六○○人か)について、のちに下里正樹氏がルポ『隠された聯隊史』(青木書店・一九八七年)の 一一五~一一八ページで明らかにしている。つまり三二八人は敗残兵だが、あと約三○○人は一般市民であった。手記の字体を否定した板倉氏には個人的事情がからんでいた。
『南京事件を考える』pp.46-54
陳万禄 (東京裁判における証言)
日本軍が南京に入城したとき、五万人余の難民と武装を解いた兵士が、燕子磯の揚子江の江岸まで逃げてきており、そこから揚子江を渡って江北へと避難できればと願っていた。だが、既にこのとき燕子磯一帯は敵軍艦の支配下にあったのだ。しかも敵飛行機は絶え間なく江岸に向かって爆撃と掃射を行い、難民たちは四方に逃げ散った。しかし思いがけないことに、南京城を陥落させた軍が雲霞のように押し寄せ、直ちに難民を砂洲中に囲い込み、そののち数十挺の機関銃を設置して掃射したため、五万人余の無幸の同胞はすべて殺害された。 死体は川面を漂い、血が大なる江流を染めた。このうち兵士は三万、他は民間人二万余である。
『南京の氷雨』 pp.150-151
唐府普 (教導総隊) (『侵華日軍南京大屠殺史稿』掲載)
南京に日本軍が入ってきた。私たちは退却に転じ、下関から船で揚子江に出たが、思うように進めず、燕子磯に漂着してしまった。燕子磯には難民があふれており、盆、桶、板などを利用して川中島の八卦洲に渡ろうとしていた。だが途中まで行くと半浮半沈状態となって徒労だった。そんなところへ日本軍が進出してきて捕えられ、連行されたのは中国軍兵士の営房だった。そこには約二万人の私と同じ運命の人々がいた。大部分は兵士だったが、民間人も含まれていた。三日三晩も給食がなく、水も与えられなかった。このため耐え切れず、老人や子供たちは死んでいった。
そして十八日の夕方、私たちは布や縄などで両手を縛られ、四人ずつつながれて歩かされた。老虎山の道をたどって大窩子の江辺に連れ出され、坐れと日本兵に指示された。殺される、縄を解いて逃げようと思った瞬間、日本兵の「殺せ」の声とともに銃撃が走った。私はつまづいて倒れ、そこに銃弾を受けた人たちが折り重なった。射撃は二十分ほど続いて停止したが、五分後に再び銃撃があった。折り重なった人たちが重い。みんな死んだのだ。日本兵はそれらの人を銃剣で突き刺し、また棒で殴りつけて歩いていた。そして最後には油をかけて火をつけ始めた。
私は折り重なった死体の下から這い出し、流れに沿って逃げた。民家のあるところまできて、誰もいない家で衣服を見つけて着替え、稲穂を見つけて飢えをしのいだ。結局は再び燕子磯で難民の老人や子供たちにまじり、小舟を見つけ、川中島(八卦洲)へと逃げ、さらに江北へと渡った。のち私は新四軍に入ったが、新四軍の話によると、幕府山付近に収容された私たちの仲間は、草鞋峡でほとんど殺され、油をかけて焼かれたとのことだった。
『南京の氷雨』 p.156-158
晋洪亮 (揚子江要塞部隊 軍医所) (『侵華日軍南京大屠殺史稿』掲載)
私たちの部隊は、南京最後の日とともにばらばらになり、私は日本軍に捕えられたが、このとき一緒に捕えられたのは三千人だった。何日か過ぎて、私たちは縄で縛られ、二十人ずつほどの一団となって次々に草鞋峡の老江口に連れ出された。たちまち銃撃が浴びせられ、私が倒れたところへ仲間たちも倒れ込んできた。銃撃が終わると、日本兵は今度は銃剣で刺しにきた。私は腹を刺され、刀で足に切りつけられた。しかし私は死んだふりをして横たわっていた。やがて日本兵は去った。私は死体の川から這い出して逃げた。
『南京の氷雨』 p.158-159
史栄禄 (民間人) (『侵華日軍南京大屠殺史稿』掲載)
私は南京に日本軍が攻めてきたとき、笆斗山鎮にいたが、日本軍に捕えられ、老虎山の下に収容された。そこには多数の人々が捕われ、集中起居していた。ある夜、私たちは江岸に引き出され、二挺の機関銃で掃射された。みんな死んで倒れたが、日本兵は一応は死体を銃剣で刺して歩いたものの、私は運よく死なずに逃げることができた。
『南京の氷雨』 p.159
殷有余
『証言・南京大虐殺 戦争とはなにか』掲載
pp.17-22
2 魚雷営の大虐殺 一九三七年十二月十五日、南京城陥落の次の日、一般人と武器を捨てた軍人九千余人は、日寇(*5)の俘虜とされたのち、海軍魚雷営まで押送され、機関銃による集中掃射を受け、殷有余ら九人が脱出したほかは全員殺害された。被害者殷有余が法廷でおこなった証言資料はつぎのように指摘している。「(農暦)民国二十六年〔一九三七年〕十一月十一日(*6)、被害者わたくしは上元門において敵に縄で縛り上げられました。わたくしと一緒に俘虜となった官兵および民衆は約三百余人で、胡姓の瓦葺きの家に押し込められました。十三日夜になって、またもや上元門外の道路沿いに追い立てられながら魚雷営の長江の端まで来た時、敵はすでに機関銃四挺を設置済みで、拉致されてきた計約九千人以上の一群の人々が行進している最中、敵はたちまち機関銃を発射し、掃射を加えたのです」(4)この時の集団大虐殺は夜間におこなわれたため、殷有余ら九人は銃声を聞いて倒れ込み、血だまりの中に横たわっていて、幸いにも銃弾に当らず、死を免れることができた。
*5 日寇とは日本侵略者の意。あえて訳さず日寇のままにした。
*6 農暦十一月は新暦十二月。
p.70
(4)戦犯谷寿夫の事案。
※K-K註:「本書は、中国人民政治協商会議江蘇省南京市委員会文史資料研究会編『史料選輯(侵華日軍南京大屠殺史料専輯)代第四輯(内部発行)一九八三年八月発行の翻訳である。」(同書「訳者まえがき」より)
『証言・南京大虐殺 戦争とはなにか』
『侵華日軍南京大屠殺史稿』掲載
第二節 魚雷営、宝塔橋の虐殺
1937年12月15日、日本軍は魚雷営で9,000人を虐殺し、その後も宝塔橋と魚雷営一帯で大規模な虐殺を行い、犠牲者の数は3万人(※)以上になった。
1937年12月15日夜、武器を放棄した9,000人以上の民間人と将兵が日本軍によって海軍魚雷営に連行され、激しい機関銃掃射を受けた。脱出した殷有余を含む9人を除き、残りは全員殺害された。大量虐殺は夜間に行われたため、殷有余ら9人は銃声を聞いてすぐに倒れ、幸い銃弾に当たらず死を免れた。
1946年10月5日、南京市臨時参議会は、日本軍が魚雷営で殷有余らを大量虐殺したことを報告した:1937年11月11日(公暦12月13日)、被害者は敵によって上元門で縛られた。将校、兵士、民間人約300人が捕らえられ、胡姓の瓦屋根の家に拘留さた。13日の夜、彼らは上元門の外まで追い立てられ、魚雷営の江岸までの道に沿って連行された。当時、敵は4丁の機関銃を配備しており、9,000人以上の集団が拘束されていた。行進中に敵が機関銃を発砲し始めたが、幸運にも殷君は虐殺から逃れた。①
1946年10月19日午後3時、南京戦犯裁判の検察官丁承網は被害者の殷有余に尋問した。彼の記録の一部は次の通りである。
問:その時、何人の人々が捕らえられましたか?
答:我々の砲台にいた約300人の将兵が一緒に捕らえられました。
問:その日、何人が捕らえられましたか?
答:この日、将校、兵士、民間人を含む9000人以上が捕らえられました。
問:これらの人々はどこへ連れて行かれましたか?
答:一緒に魚雷営へ連れて行かれました。
問:魚雷営へ連行された後、何をされましたか?
答:日本兵は4挺の機関銃で発砲しました。死ななかったのはわずか9人で、私もその1人でした。
問:その時、怪我はありましたか?
答:他の死体の下敷きになったため、怪我はありませんでした。
問:いつ逃げたのですか?
答:その夜の10時過ぎに日本軍は去っていきました。第36師の除班長も死を逃れ、私のロープを外して一緒に逃げました。この時逃げた他の7人は全員重傷を負っていたました。
問:これらの人々は全員機関銃で射殺されたのですか?
答:その人たちは全員殺されました。私の父だけは年を取っていて歩けなくなり、路上で日本兵により刀で殺されました。①
①国民政府档案、中国第二歴史档案館蔵。
『侵華日軍南京大屠殺史稿』p.19 |
『侵華日軍南京大屠殺史稿』p.20 |
 |
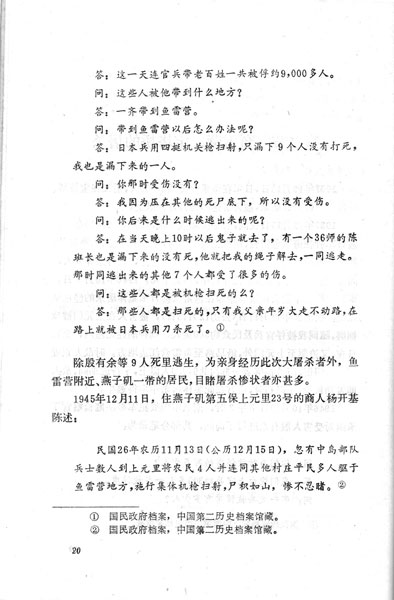 |
※K-K註:原文では「30,000万人」と書かれているが誤植と思われので「3万人」と修正した。
『侵華日軍南京大屠殺史稿』pp19-20
『侵華日軍南京大屠殺档案』掲載
殷有余が軍事法廷で陳述した魚雷営での日本軍の大量虐殺の状況
(1947年2月8日)
問:姓名、年齢は?
答:殷有余、85歳、燕子磯に住んでいます。
問:あなたは法廷に出たことはありますか?
答:具〔シンニュウ+寸〕結的
問:日本軍による大量虐殺について簡単に説明してもらえますか?
答: それは旧暦の冬月11日の午後4時でした。日本兵は川沿いの魚雷営で9000人以上の人々を虐殺し、次に銃剣で刺し、最後に灯油で焼き殺しました。
問:実際に見たことがありますか?
答:死体の山から逃げました。
『侵華日軍南京大屠殺档案』p.109
『南京の氷雨』掲載
九千人の虐殺。しかし、この中に生存者がおり、この『侵華日軍大屠殺史稿』(K-K註:ママ)にもその状況が記録されていて、殷有余さんら九人の惨劇の思い出が収録されている。ここでは極東軍事裁判(※)での殷さんの証言(先に別の形で紹介してあるが、部分的に再録)を紹介する。
―― 何人ぐらいで、どのようにして日本軍に捕えられましたか。
殷 私たちは砲台を守っていたが、三百人が一緒に捕虜になりました。その場所は上元門でした。
―― どんなところに収容されたのですか。
殷 私は胡という姓の家に押し込められましたが、全部で九千人いました。そこには老農など民間人も含まれていました。
―― 収容後、いつ、どんなことがあったのですか。
殷 魚雷営に連れて行かれました。たしか十五日夜のことでした。そこには機関銃四挺が据えられており、連行される途中から銃撃がはじまったのです。私たちは銃声と共に倒れ込み、死んだ人々の血だまりの中に伏していました。そう、あれは夜十時ごろのことでした。
―― それで、どうしました。
殷 死んだふりをしていたのです。日本兵はやがて去りました。私たち生き残った七人は助け合い、恨みの場から立ち去ったのです。
※K-K註:ここでは「極東軍事裁判」としているが、引用元である『侵華日軍南京大屠殺史稿』(p.19)では南京軍事法廷の尋問となっている。
『南京の氷雨』 pp.160-161
|